1月 元旦
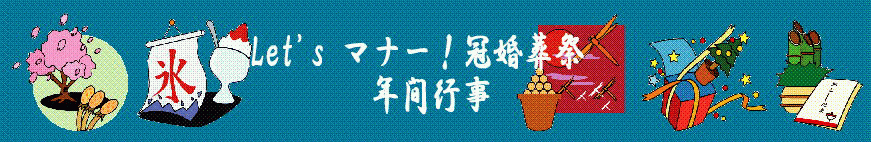
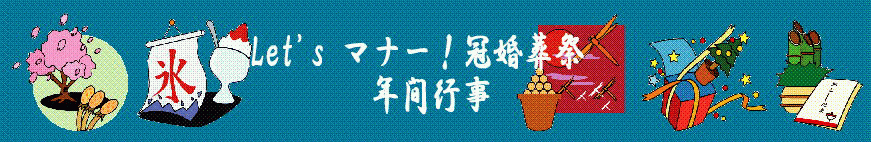
◆1月・睦月(むつき)は、仲良く親しみあうということが語源で、お互いにいったりきたりして親しみを深めるという意味があります。 睦月は日本古来のお正月の呼び名で、昔は、正月や1月という言葉は使われなかったということです。 正月の祝は、新しい年の神が家々に降りて、その年の健康と幸福を授ける、という言い伝えが日本にあります。 そのために年末から大掃除をし、家を清め、餅をついてお供えの準備をします。
★★◇正月はなんといっても おせち料理ですね。
「お節(おせち)」とは、節句にいただく料理や神に供える料理のことです。
正月のおせち料理は、神を迎え、神とともに元旦を祝い、神にそなえたご馳走をみんなでいただいて、幸せを祈るという意味。
正式なおせち料理は、四段重ねで、柳箸と呼ばれる両端が細く丸くなった祝箸を使います。
これは、一方は、人が使い、一方は神が使うという意味です。
最近のおせち料理は、手間と時間がかかる料理は、お店で買う人が増えているようです。
和食だけでなく、洋風、中華風のお節も人気が高いようです。
★お節・重箱の盛り付け
一の重(祝肴)《黒豆・数の子・ごまめ(田作りともいう)・たたきごぼう》など
二の重(口取り)《きんとん・だてまき》などの甘いもの
三の重(海の幸)《たい・ぶり・いか・えび・昆布・あわび》など
与の重(山の幸)《八つ頭・こんにゃく・さといも・蓮》など
※四は縁起が悪いので与と書く
★お正月に食べると縁起のよいもの
黒豆・・・無病息災
数の子・・・子孫繁栄
五万米・・・五穀豊穣
きんとん・・・財産がたまる
昆布巻き・・・ 喜ぶ
紅白なます・・・平和
たたき牛蒡・・・豊年.息災
蓮・・・見通しがきく
八つ頭・・・人の上にたつ
伊達巻・・・教育 文化が身につく
海老・・・長寿
★正月飾りはいつ外す?
正月飾りを取り外すのは、正月をひと区切りするという意味で7日目が多いようです。
6日までを「松の内」といいます。
しかし、地方によって違いがあります。
初詣は松の内に神社やお寺に行き、お参りしましょう。
☆☆☆ 神社への参拝の仕方 ☆☆☆
1、手水(ちょうず)を使い、左手、右手の順に水をかけ、もう一度左手に水を受け、口をすすぎます。
2、お賽銭を入れます。
3、右手で鈴の綱を持ち 鳴らします。
4、神前に2回礼をし、2回手を打ち、合掌して、もう一度礼をします。
★年始回り
正月は、家族で過ごすというのが一般的な考え方ですから、年始の挨拶は元旦は避けたいものです。
あらかじめ先様の都合を聞き、2日から7日の間にしましょう。 訪問時間は、お昼時を除いた10時ごろから夕方5時くらいまでとします。
年始の挨拶は、玄関先で失礼するのがマナーです。「お上がりください」といわれても、お宅に上がってはいけません。
万が一不在だったときは、持参した品は持ち帰り、郵便受けに年始の挨拶と、名前・日時を書いたものを入れておきましょう。 このようなことがないように、先様の都合を聞いておくことが大事です。