年間行事 5月 皐月
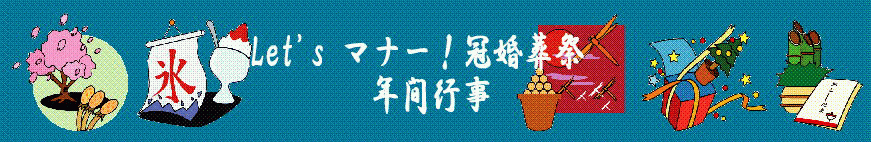
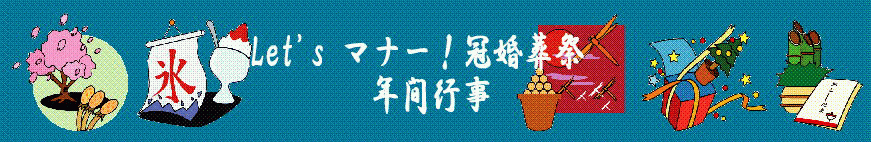
◆5月は田植えの季節で、早苗を植える月ということから 早苗月と呼ばれ、 略されて、さつきとなったようです。
★★◆端午の節句
現在では、「こどもの日」とよばれ休日になっています。
本来は厄除けの行事です。
武家社会の時代、武士の間で「菖蒲」と「尚武」をかけて、端午の節句を尚武の節日と考えるようになり、端午の節句が男の子のお祝いになっていったようです。
兜鎧は命を守る つまり 事故や災害から命を守るという意味で、こいのぼりは、「滝をのぼる鯉のようにたくましく育つように」という気持ちが込められているのです。
また、子供の健康を願い、邪気をはらい厄難を除くといわれる、菖蒲湯に入る習慣があります。
菖蒲は香りがよく、血行促進、腰痛や神経痛をやわらげる働きもあるようです。
近頃はゴールデンウィークのほうが大きなイベントのようになっていますが、
五月人形を飾って節句を祝う家庭も まだ多くあります。
一夜飾りにならないよう、4月半ばの大安や友引きに 飾りましょう。
※1ヶ月ほど前から飾って、節句後の天気のよい日にかたづけますが、お守りとして1年中飾っておいてもいいです。
祝い膳は、魚料理なら出世魚の ぶり、すずき、ぼら、かつおなど。
野菜は、たけのこが好まれます。元気ですくすく育つようにということでしょう。
◆柏餅とちまき
柏もちは、端午の節句の祝い菓子で、関東でよく用いられます。
関西は、ちまきのほうが一般的のようです。
柏の葉は、新芽が出ないと古い葉が落ちないことから、子ができるまで親が死なない、つまり、家計が途絶えないという意味の縁起物として、端午の節句には子孫繁栄を願って用いられます。
◆母の日
アメリカのある女性が 母の命日に、母の好きだった白いカ−ネーションを飾り、母に感謝したことがきっかけで正式な行事になったといわれます。
日本では終戦後に 一般でも祝うようになりました。
赤いカーネーションは定番ですが、お母さんが亡くなっている人は白いカーネーションです。
赤は「母の愛」白は「亡き母をしのぶ」という花言葉があります。