年間行事 4月 卯月
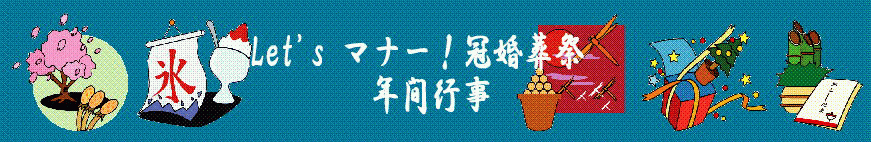
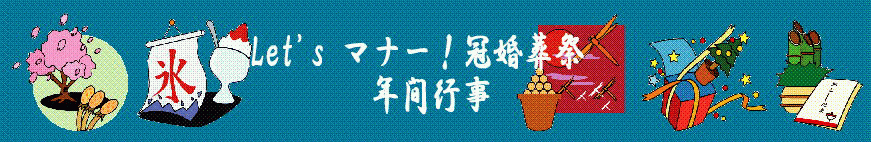
◆4月・卯月(うづき)とは、卯の花が咲く月、 また、卯は 十二支の4番目であるからとか 苗を植える月、植月(うつき)からきているなどの説があります。
★★◆エイプリルフール(1日)は、世界的に唯一嘘をついてもよい日とされ、 だまされた人をエイプリルフールと呼ぶのだそうです。 その起源はというと、キリストが生前、 ユダヤ人に愚弄されたことを忘れない為の行事とする説が有力とされていますが、 さだかではないようです。
◆花祭り(8日)は、お釈迦様の誕生日を祝う仏事ですが、 仏教では、潅仏会(かんぶつえ)といい 各地のお寺で 「生まれたばかりのお釈迦様に 九竜が天から香湯をそそぎ産湯とした」 という伝説にちなみ、中央に安置された釈迦誕生仏像に 参拝者が、甘茶をかけます。 ※5月8日に行う地域もある。
◆十三参り(13日)は、江戸時代から続く習慣です。 陰暦の3月13日に、数えの13歳の男女が 親子に知恵を授けてくれるという 虚空蔵菩薩にお参りをする日です。 子供から大人になっていく頃で、厄除けの意味もあり、 晴れ着を着る女子も多く見られます。 関西地方で多く行われる行事で、関東では一般的ではないようです。
◆イースター(13日頃)は、キリストが死から復活したことを祝う、 キリスト教最大のお祭です。 イースターの日の決め方は、地方によって違いますが、欧米では主に 春分の日の後の 最初の満月から数えて1番目の日曜日です。 子供たちにとって、とても楽しいもので 卵に絵付けしたり、 その卵を隠して 探したりする遊びがあります。
草もちの作り方
材料(15〜16個分) 生よもぎ・・・70g 重曹・・・ひとつまみ
こしあん(市販)・・450g 上新粉・・・200g 白玉粉・・・40g
作り方
・よもぎは葉先の柔らかい部分だけをつみとり、よく洗っておきます。 たっぷりの湯に重曹を加えゆで、水にさらしてアクを抜きます。 よく絞って、みじん切りか、すり鉢でよくすります。 ミキサーにかけてもいいでしょう。
・こしあんは15〜16等分し、まるめておきます。
・上新粉をボールにいれ、熱湯1カップを少しずつ加え、木べらでまぜていきます。
・別のボウルに白玉粉を入れ、水 おおさじ強をいれよくこねたら、 上新粉とあわせ、よくこねます。 これを一握りの大きさにちぎります。
・蒸気の上がった蒸し器に濡れふきんをしき 並べて蒸します。強火で約10分。
・中まで透き通った感じになったら、蒸し上がり。 ふきんごと上げて、水にくぐらせ さっとひきあげます。 すり鉢かボールに入れ、これを熱いうちにすりこ木などで、突いて混ぜます。
・生地がまとまったら、手でよくこね よもぎを加えてさらにこねましょう。 これを こしあんの数分に等分します。
・生地を薄く延ばし、こしあんを包んでいきます。
※ポイント
生地が熱いうちに あんを包みます。 乾燥よもぎを使うときは、15〜20gを水かぬるま湯でもどしてつかいます。